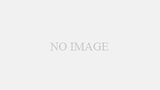はじめに
今、大地震や集中豪雨や洪水等の水害、事業所内での新型コロナウイルスによるクラスターの発生、テロ等の不測の事態に見舞われた状況になった場合、あなたの事業所は生き残る自信がありますか。。従業員やその家族を守れますか。お客様からの信頼を維持できますか。
そのような状況に自分たちが置かれるかもしれないと思いながらも、どこか他人事のように考えていませんか?
近年、大地震や大雨による河川の氾濫や洪水で介護施設や事業所が被害を受けるケースが毎年のように起こっています。
何らかの災害に被災するかもしれないということは、決して他人事ではない事を肝に銘じておかなえればなりません。

業務継続計画(BCP)とは
あなたが、事業所の経営に携わる立場であれば、こうした緊急事態に遭っても、何とかしてサービスを続られるようにしなければなりません。しかし、いざ緊急事態という時に、あなたは普段と同じように判断し、的確な行動ができるでしょうか。
あなたが冷静であっても、従業員はどうでしょう。あなたの事業所の従業員は、自分の置かれている状況に合わせて、実行してもらいたいアクションができるでしょうか。
緊急事態で的確に判断し行動するためには、緊急時に行うべき行動や、緊急時に備えて平常時に行うべき行動をあらかじめ整理し取り決めて置かなければなりません。
この、事前の取り決めをまとめたものが「業務継続計画(BCP)」です。
業務継続計画(BCP)と介護事業の継続
BCPはBusiness Continuity Plan の略で一般企業では「事業継続計画」、厚生労働省は介護や医療向けに「業務継続計画」と略しています。
BCPは、あなたにとって決して特別なものではありません。例えば、普段あなたが病気で入院したら事業所をどのように続けていくか考えたことはありませんか。
BCPはそのような、あなたが日々の経営の中で考えていることを、計画として「見える化」しておくのです。最高意思決定者が不在というのは緊急時事態です。そのような場合に、従業員が業務を続けるためのツールがBCPです。
したがって、BCPは日々の経営の延長にあるものと考えられます。
事業継続とマネジメント
緊急事態では、必ずしもトップダウンで指示が受けられる訳ではありません。経営者が被災してしまう、通信手段が断絶して連絡が取れfない等はよくある話です。
そのような状況で的確に判断し行動するためには、緊急時に行うべき行動や、緊急時に備えて平常時に行うべき行動をあらかじめ整理し取り決めておきます。
ただし、「業務継続計画(BCP)」は策定するだけでなく、きちんと運用できるようにしておくことが重要です。

有事の時に生き残れる事業所にするには
大きな企業が運営しているような事業所や、何千人も従業員がいる大規模の事業者では既に組織的にBCPに対応するべく行動を取られてることでしょう。
また、幾つも事業所を運用している大規模な組織では、被害が分散され、被災した事業所に物資や人員の応援を出すことができることも多いです。
しかし、中小の介護事業者は地域に根ざした運営を行い、狭い範囲で事業所を開設している事業者がほとんどです。一つの事業所だけを運用しているところもたくさんあります。
中小の事業者では資金、人員、物資などあらゆる面で大きな事業者とは違いがあります。業務の継続ができない期間が長くなれば、事業の継続が困難になる事は間違いありません。
実際に新型コロナウイルスのクラスターが発生した介護事業所の多くがその後の事業所経営に支障をきたしています。
そのようなこともあり、令和3年の介護報酬改定ではついに介護事業者にBCPの策定が義務付けられました。3年間は努力義務とされています。
中小企業の経営者の方々こそ、BCPの必要性をしっかりと認識しなければなりません。この3年間は、日々BCPにしっかりと取り組む努力をしなければならない期間と捉えるべきだと思います。
出来るだけ早急にBCPを策定し、そして策定したBCPを日常的に運用(教育訓練や計画の見直し)できるようにしていきましょう。
それこそが、何らかの有事が発生した場合でも中小の介護事業者が生き残っていくための、必要不可欠な経営戦略のひとつであると言えるでしょう。